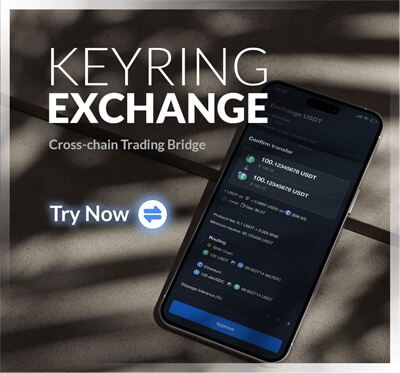モジュラーブロックチェーンとは?モノシック型との違いやレイヤー2などとの関係について解説

ブロックチェーン技術は、ビットコインやイーサリアムの登場以降、分散型アプリケーション(DApps)やスマートコントラクトの基盤として急速に発展してきました。しかし、その成長の過程で「スケーラビリティ」「分散性」「柔軟性」といった課題にも直面してきました。特に、すべての処理を1つのネットワークに集中させる「モノリシック型」アーキテクチャには限界があり、より高度で効率的なインフラの必要性が高まっています。
こうした背景の中で注目を集めているのが、「モジュラーブロックチェーン」という新しい設計思想です。これは、ブロックチェーンの主要な機能を分離し、それぞれを専門のレイヤーやプロトコルが担うことで、柔軟かつスケーラブルな分散型システムを実現しようとするアプローチです。
本記事では、モジュラーブロックチェーンの基本概念から、既存モデルとの違い、技術構成、注目のプロジェクト、さらには今後期待されるユースケースまでを包括的に解説します。これからのWeb3時代を支える基盤技術として、モジュラーブロックチェーンの全体像を掴んでみましょう。
モジュラーブロックチェーンとは?
モジュラーブロックチェーンとは、ブロックチェーンにおける機能(実行、合意形成、データ可用性、決済)を分離・分担することで、スケーラビリティや柔軟性を向上させる新しいアーキテクチャです。
従来のブロックチェーンは、これらすべての機能を一つのチェーン(ネットワーク)が処理する「モノリシック型」が主流でした。しかし、この構造では拡張性に限界があり、特に以下のような課題が指摘されていました。
- ノードの処理負荷が高く、参加のハードルが上がる
- トランザクション処理能力(TPS)が限られる
- カスタマイズ性が乏しく、新しいユースケースへの対応が困難
こうした背景から誕生したのが「モジュラーブロックチェーン」です。このモデルでは、異なるチェーンやプロトコルが特定の機能に特化し、それぞれのレイヤーを連携させることで、全体として高性能な分散型ネットワークを実現します。
モノリシック型との違い

- 実行の違い
モノリシック型:トランザクションの実行をチェーン自身がすべて担う
モジュラー型:実行はロールアップなど実行レイヤーに分離されている - 合意形成の仕組み
モノリシック型:合意形成(コンセンサス)はチェーン内部で完結
モジュラー型:コンセンサスレイヤーと連携することで構成を柔軟にできる - データ可用性(Data Availability)の扱い
モノリシック型:チェーン自体がトランザクションデータを保持・配信
モジュラー型:CelestiaなどのDAレイヤーにデータの保存と配信を任せる - 柔軟性
モノリシック型:設計や仮想マシンに制限があり、カスタマイズが難しい
モジュラー型:各レイヤーを用途に応じて自由に選択・構成できる - スケーラビリティ
モノリシック型:性能を上げると分散性やセキュリティとのバランスに限界がある
モジュラー型:処理を分散することで、高いスケーラビリティを実現しやすい
モノリシック型では、すべてのノードが全機能を処理するため、スループット(処理能力)を上げようとすると、分散性が犠牲になりがちです。一方、モジュラーブロックチェーンでは、各機能を専門化し、それぞれが独立してスケールすることが可能になるのです。
4つの機能レイヤーの解説

モジュラーブロックチェーンの核は、「4つの役割の分離」にあります。それぞれの役割と担当レイヤーは以下の通りです。
① 実行(Execution Layer)
ユーザーのトランザクション(例:トークン送金やスマートコントラクト)を実行・処理するレイヤーです。多くの場合、ロールアップ(Rollups)と呼ばれる技術が使われます。
② 決済(Settlement Layer)
実行結果に対する最終的な合意や紛争解決を担います。例えるなら「裁判所」のような存在で、ロールアップから送られてきた結果を確認し、最終的な処理として記録します。
③ 合意形成(Consensus Layer)
ネットワーク内のノードが、どのブロックを正とするかを合意するためのレイヤーです。PoS(Proof of Stake)などの仕組みを使い、順序や正当性を保証します。
④ データ可用性(Data Availability Layer)
ブロックに含まれる全トランザクションのデータを安全に保管・配信します。これが機能しないと、ロールアップや検証ができず、セキュリティの根幹が崩れます。
このようにレイヤーを分けることで、それぞれが独立に改善・最適化される余地が生まれます。
ロールアップやレイヤー2との関係性

モジュラーブロックチェーンの文脈において、最も重要な実装例のひとつが「ロールアップ(Rollups)」です。ロールアップは、従来のLayer1(L1)ブロックチェーンと比較して、処理能力の拡張性とアプリケーション開発の柔軟性を両立させる仕組みとして注目を集めています。特にモジュラーブロックチェーンの構造においては、「実行レイヤー(Execution Layer)」としての機能を独立させる中核的存在となっています。
ロールアップとは?
ロールアップとは、トランザクションの実行をLayer1とは別の環境で行い、その結果だけをL1に投稿(コミット)するスケーリング技術です。これにより、L1の処理負荷を軽減しつつ、L1のセキュリティや決済機能を引き継いだ形でトランザクションを処理することができます。
特にモジュラー設計では、ロールアップが実行のみを担い、合意形成・データ可用性・決済といった他の機能を外部レイヤーに任せることで、構成の柔軟性とスケーラビリティを両立することが可能になります。
ロールアップの種類
ロールアップには主に2つの方式があります。
- オプティミスティック・ロールアップ(Optimistic Rollups)
- トランザクションは一旦「正しい」と仮定して実行され、一定期間内に異議申し立てがなければ確定。
- チャレンジ期間中に検証者が不正を発見すれば、ロールバックが可能。
- 例:Optimism、Arbitrum
- ゼロ知識ロールアップ(ZK Rollups)
- トランザクションの実行結果と一緒に、正当性を数学的に証明する暗号的証明(ZK-SNARK/ZK-STARK)を生成してL1に送信。
- チャレンジ不要で即座に検証・確定が可能。
- 例:zkSync、Starknet
モジュラー構造との関係
モジュラーブロックチェーンの世界では、ロールアップは単なるL2スケーリング手段に留まりません。特に次のような構成が実現されています。
- 実行(Execution):ロールアップが担当(各アプリごとに最適なVMを選択可能)
- データ可用性(DA):CelestiaやEigenDAといった外部DAレイヤーを活用してコスト削減&高スループット化
- 合意形成(Consensus)・決済(Settlement):EthereumなどのL1、または任意のL2や独立型レイヤーに委ねる
このように、ロールアップはモジュラーブロックチェーンの実行レイヤーとして、他の機能と切り離され、自由に組み合わせ可能な存在として機能します。
注目プロジェクト:Celestia、Dymensionなど
モジュラーブロックチェーンのアーキテクチャを現実のプロダクトとして実装しているプロジェクトは、今後のWeb3インフラの方向性を示す重要な存在です。ここでは、特に注目されているCelestiaとDymensionを紹介します。
Celestia(セレスティア)
Celestiaは、世界初の「モジュラー型データ可用性(DA)レイヤー」として設計されたLayer1ブロックチェーンです。その最大の特徴は、スマートコントラクトやトランザクションの実行は一切行わず、データ可用性とコンセンサス機能の提供に特化している点にあります。
主な特徴と技術構成
- Execution-Free Layer1:自らはスマートコントラクトを一切実行せず、他のロールアップやAppChainのデータを受け入れて配信する「データ専用のLayer1」。
- Data Availability Sampling(DAS):ノードは全データを保持せずとも、一部のデータ断片を検証することで“全体の存在”を確率的に保証。これによりライトクライアント(スマホなど)でもDA検証に参加可能。
- Namespaced Merkle Trees(NMT):異なるRollupから投稿されたデータをブロック内で分離・効率的に管理する構造。
位置づけ
Celestiaは、Rollupやアプリ専用チェーンの「データの保存・配信基盤」として機能することで、ブロックチェーンのスケーラビリティと分散性の両立を支える“土台”となります。「自ら意味は持たないが、“意味あるチェーン”を支える」それがCelestiaの革新性です。
Dymension(ディメンション)
Dymensionは、「RollApps」と呼ばれる新しい実行環境モデルを中心に据えたモジュラー構造を民主化するプロジェクトです。誰でも自分の用途に特化したRollup(RollApp)を簡単に立ち上げられるように設計されており、ブロックチェーンのApp化を加速させる構成になっています。
構成要素
- RollApp(実行レイヤー):EVMやWASMなど任意のVMを採用可能。アプリのニーズに最適化された独自環境を構築できる。
- Dymension Hub:各RollAppを統合的に扱うレイヤーで、合意形成や決済、クロスRollApp通信を担う“ハブ”の役割。
- 外部DA対応:Celestiaなどの外部DAレイヤーとの統合を前提とした設計で、スケーラビリティとコスト最適化を実現。
位置づけ
Dymensionは、まさにモジュラーブロックチェーン時代の“WordPress”のような存在を目指しており、「アプリ特化チェーン構築の低コード化」によって、開発者・スタートアップがチェーンを当たり前に持つ時代を実現しようとしています。
この2つのプロジェクトは、モジュラーブロックチェーンという思想を別々の方向から具体化しています。
- Celestiaは「チェーンを支えるチェーン」
- Dymensionは「誰もがチェーンを作れるようにするためのプラットフォーム」
どちらも、今後のWeb3のスケーリングと分散型アプリケーション開発の進化を大きくリードしていく存在といえるでしょう。
モジュラー設計のメリットと課題

モジュラーブロックチェーンは、従来のモノリシック型が抱えていた「スケーラビリティの壁」を乗り越える画期的なアプローチですが、当然ながら課題も存在します。ここではそのメリットとデメリットを整理します。
モジュラー設計の主なメリット
① 圧倒的なスケーラビリティ
実行・検証・合意形成などの機能を分担することで、個々のレイヤーが独立して拡張可能になります。これにより、トランザクションのスループットを大幅に向上させられます。
② 柔軟性と開発自由度の高さ
開発者は、自身のアプリケーションに最適なバーチャルマシン(VM)や言語スタックを選択可能。EthereumのEVMに縛られることなく、WASMや独自VMを導入する事例も増えています。
③ インターネットのような構造(Interoperability)
異なる機能を持つレイヤー同士が組み合わせ可能で、再利用もできるため、複数のチェーンをまたぐエコシステムが実現しやすくなります。
④ ロールアップとの高い親和性
モジュラーデザインは、ロールアップの信頼性や性能を最大限に引き出すための理想的な構造でもあります。
モジュラー設計の主な課題
① 技術的な複雑性
各レイヤーを組み合わせる設計は柔軟である一方で、開発や運用の難易度が高いのも事実です。特に初学者にとっては、アーキテクチャの全体像が掴みにくくなりがちです。
② エコシステムの未成熟
CelestiaやDymensionのようなプロジェクトはまだ実験段階やテストネットでの運用が多く、商用・大規模利用が進んでいるとは言い切れません。
③ 断片化によるセキュリティ懸念
モジュラー設計では、各レイヤーが異なる主体により運用されることもあります。これにより、信頼や整合性に関する新しい課題(例:データ可用性の不正や不一致)が生まれる可能性があります。
モジュラー型は「万能の答え」ではなく、設計思想や目的に応じた最適解の一つとして評価されるべきです。
モジュラー化が拓く未来のユースケース

モジュラーブロックチェーンは、その柔軟な構造により、これまでのブロックチェーンでは実現が難しかった多様な応用分野やスケーリング戦略に光を当てています。以下では、いくつかの注目すべきユースケースを紹介します。
アプリケーション特化型チェーン(App-specific Chains)
アプリケーションが自前のロールアップ(RollApp)や実行レイヤーを持つことで、自分たちに最適化されたバーチャルマシンや処理モデルを選べます。
- 例:ゲームチェーンが高速性と柔軟性を重視したVMを採用
- 金融DAppがより堅牢な決済・合意モデルを利用可能に
これにより、「アプリごとのブロックチェーン最適化」という新しい開発パラダイムが生まれます。
分散型インフラとしてのデータ可用性
Celestiaのようなプロジェクトが提供する「データ可用性レイヤー」は、将来的に以下のような汎用的な分散データストレージ基盤になる可能性があります。
- チェーン間の安全なブリッジ(クロスチェーン通信)
- オフチェーンコンピューティングの検証
- フラグメント化したロールアップ間での状態同期
分散ストレージとブロックチェーンが“再統合”されるまさにWeb3の根幹に関わる進化です。
L3(レイヤー3)によるフラクタルスケーリング
モジュラー構造が普及すれば、L1(基盤)→ L2(ロールアップ)→ L3(L2上のアプリ専用チェーン)という多層構造も現実的になります。
- DeFiアプリA、ゲームB、NFTマーケットCがそれぞれL3で展開
- 各L3は同じL2上で構築されるため高速かつ安価で相互運用可能
これはまさに、分散型アプリケーションのクラウドインフラ化と呼べるビジョンです。
セキュリティの選択可能性(セキュリティ・アズ・ア・サービス)
モジュラーブロックチェーンは、必要に応じて異なるセキュリティモデルを選択できるようになります。たとえば
- 高セキュリティを要求する金融DApp → Ethereum L1を決済に使用
- 高スループットが求められるゲーム → Celestiaなどに依存
セキュリティすら「サービス」として選ぶ時代へ。これはインフラとしてのブロックチェーンを再定義する発想です。
よくある質問(Q&A形式)
Q1. モジュラーブロックチェーンは既存のブロックチェーンと何が違うの?
A:既存のブロックチェーン(モノリシック型)は、1つのチェーンが「実行・合意・データ可用性・決済」すべての機能を担います。それに対してモジュラーブロックチェーンは、これらの機能を専用のレイヤーに分離し、それぞれの機能に特化したネットワークが連携することで、柔軟かつ効率的なシステムを構築します。
Q2. Celestia はどのように使われているの?
A:Celestiaは「データ可用性とコンセンサス」に特化したモジュラー基盤です。自らスマートコントラクトを実行したりはせず、ロールアップや他のチェーンが生成するトランザクションデータを安全かつ効率的に保存・配布する役割を果たします。これにより、L2やL3がCelestiaをバックエンドとして利用できるようになります。
Q3. モジュラーブロックチェーンは将来的に主流になるの?
A:可能性は非常に高いと見られています。特に「スケーラビリティ」「柔軟性」「分散性」の3つの課題(=ブロックチェーン・トリレンマ)を解決できる設計として期待されており、EthereumやCosmosといった既存エコシステムも部分的にモジュラー化の方向に進んでいます。
Q4. モジュラー設計にはリスクはないの?
A:はい、いくつかあります。例えば、レイヤー間の通信の信頼性、セキュリティの分散によるリスク、設計や開発の複雑化などが挙げられます。特にデータ可用性レイヤーの正当性が損なわれると、実行レイヤー全体が影響を受ける可能性もあります。
まとめ:モジュラーブロックチェーンはWeb3の“クラウド革命”
モジュラーブロックチェーンは、Web3の成長におけるインフラの再設計とも言える存在です。
- スケーラビリティを圧倒的に向上
- 柔軟で多様な開発環境を提供
- セキュリティや処理コストを用途に応じて最適化
- モジュール単位で自由に組み合わせることで、「自分に最適なブロックチェーン構成」が可能に
今後は、DeFiやNFT、GameFiだけでなく、実社会のインフラやIoT、メタバース基盤にも応用が期待されています。
この記事が「モジュラーブロックチェーン」についての理解を深める一助となれば幸いです。